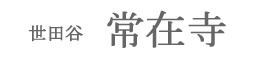【お盆】お盆のはじまりは?

7月に入ると暑さも質が変わって、本格的な夏の訪れを感じます。
夏と言えば、お盆。
お盆と言えば、夏。
ということで、今回はお盆についてご説明します。
お盆ってなに?
お盆は正式には「盂蘭盆(うらぼん)」と言います。
ご先祖様の霊を自宅にお招きして、お供え物をし、お経をあげて供養する大切な行事です。
地獄に落ちたお母さんを助けたかった? お盆のはじまり
お盆の始まりについては諸説ありますが、仏教ではお釈迦様の弟子が地獄に落ちたお母さんを救ったという説話があります。
昔、目連尊者というお釈迦様のお弟子さんが神通力でお母さんの様子を見てみると、地獄で苦しんでいる姿がありました。
あわててお母さんを助けようとしますが、できません。
目連尊者がこのことをお釈迦様に伝えると、お母さんを救うには7月15日に、大勢の僧侶とともに法要をするようにと言われました。
そこで、お母さんだけでなく苦しんでいるほかの人たちのために、食べものと飲み物を用意し、僧侶たちと共に法要を行ったところ、お母さんは救われました。
こうして、夏のこの時期に、お盆の法要が行われるようになったというお話です。
日本で一番初めに公に行われたお盆は、606年の推古天皇の時代と言われています。さらに、聖武天皇の治世では、宮中の恒例行事となりました。
苦しんでいる人を供養する、お施餓鬼
お盆というと、お墓参りなどでお寺に足を運ぶ方も多いと思います。
暑い時期ですので、水分補給はこまめにとって、熱中症対策はしっかりとってくださいね。
さて、多くのお寺ではこの時期、お施餓鬼(せがき)を行います。
餓鬼(がき)というのは、いつもお腹を空かせていて、のどが渇いています。飢えと渇きに苦しんでいる亡者です。
生きている間の悪い行いによって餓鬼道という地獄に落ち、こうした苦しみを与えられていると考えられています。
施餓鬼というのは、このように苦しんでいる亡者、無縁となった亡者にも食べものや飲み物などの供物を施し、お経を読んで供養する、大切な仏教の行事です。
7月と8月、お盆はいくつあるの?
東京ではお盆を7月に行う家庭が多いと思いますが、地域によっては8月に行うこともあります。
お盆休みも8月15日前後が多いですよね。
さらに、旧盆もあります。
どうしてお盆が何回もあるのかというと、日本の暦、つまりカレンダーが、明治時代に大きく変わったからです。
それまでは「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」という暦を使っていました。
これは月の満ち欠けを基準にしながら、太陽の動きで閏月(うるうづき)を入れて、ずれを修正するというものです。
ところが日本の近代化を進めていた明治政府が1873年から、欧米と同じように、太陽の動きを基準にした「太陽暦(たいようれき)」を用いることに決めました。
切り替えの時には、「明治5年12月3日」となるべき日がいきなり「明治6年1月1日」と、突然、1ヵ月も暦が早まってしまいました。
12月がたったの2日間しかなく、いきなりお正月になってしまったので、皆ビックリしてしまいました。
でも、日付は変わっても、季節は変わりません。
特に気候と深く関わりのある農業では、昔からの暦をもとに年間のスケジュールをたてていました。
ですから、急に暦が変わってしまうと、それまでのお盆は農作業も一段落ついたころに行われていたのが、新しい暦通りにお盆を迎えてしまうと、繁忙期に当たってしまいます。
そこで、1ヵ月遅らせて、8月15日を中日として、お盆を迎えることになりました。
こうして、新しい暦のお盆(7月)と、昔の暦のお盆(8月)と2つのお盆ができて、今に至っています。
年によって日程が変わる旧盆
さらに、もうひとつ、旧暦のお盆もあります。
こちらは、昔の暦通りに迎えるお盆です。
月の満ち欠けをもとに日を定めている旧暦は、今使われているカレンダーとの差が毎年変わります。
そのため、お盆が9月になるという年もあります。